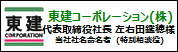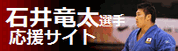ー2025年ー
2025年
3月
30日
日
60代の私が40代の私に伝えたいこと

社内の人事改革を行いました。複数の40代の社員達が役職に就くなど、組織の若返りができたように思います。
そこで今回のブログは、今60代の私が、40代の頃の私自身に伝えたいことを書いてみようと思います。
もっと若い時に知りたかったな・・・と私が思った事柄です。
タイムマシーンに乗って過去に戻って40代の私に伝えることは叶いませんが、これから成長していく社員達の未来の一助になれば幸いです。
■積極的に色んな場所に出かけて、多種多様な人達と出会え
当時の私は自分と同じカテゴリーの人としか付き合っていませんでした。話が合わない人と付き合うのは苦痛で、それきりにしていました。それどころか勝手な先入観を持って相手を見て、避けてしまうようなこともありました。
けれどもある出会いで、自分と環境や考え方が違う相手ほど、学びが多いということを知りました。相手の考え方や違う世界を知ることで、自分の世界もまた広がったような感覚がありました。
忙しさを言い訳にせず、体力のあった若い時に無理をしてでも、もっと積極的に人付き合いをすれば良かったと感じています。
■見落としがち!年下の人脈を作れ
私は20代で経営者になった為、周りの経営者は年上ばかりでした。
多くの諸先輩方に何度も助けられながら、これまでやって来ました。だからなのか、なぜか50歳を過ぎても自分のことを「若手経営者」だと思い込んでいました。
しかしある時、遅ればせながら、とある事に気付いてゾッとしました。
気付いたキッカケは、仲良くしていた年上の方が役職から引退された後、その会社からの受注の回数が突然減ったのです。
年上の方達は自分よりも先に引退するという事を忘れて、年上の重役の方達とのお付き合いにウエイトを置いていました。
私の40代はアッと言う間に過ぎ去り、50代はその倍の早さで過ぎ、気が付けば自分がその場で一番最年長という場面も多くなってきました。
時が経つのは年々、想像以上に早いです。
今40代の皆様も、アッと言う間にやって来る10年後の自分のためにも、年下を目に掛け応援し、年上だけでなく年下との人脈も作ることをお勧めします。
■情報は不可欠! 情報感度を高めよ
企業の経営資源を構成する要素は「人・モノ・金」と言われていましたが、いつの頃からか、この要素に「情報」が付け加えられるようになりました。
しかし当時の私は、自分の仕事が社会全体の動きと連動しているという感覚が薄く、恥ずかしながら「情報」についてはあまり意識していませんでした。
40代の私が見えていた社会は狭く、自分がいる業界=社会のような感覚でした。
しかし近年とくに感じることですが、グローバル化とインターネットの発達によって、情報が瞬く間に広まり、地球規模の共通意識が生まれたりします。
例えば、SDGsの普及はその典型例と言えます。(現在トランプの影響で逆回転の動きがありますが・・・)
企業の価値を測る新しい評価項目になっている側面もありますし、新商品や新企画を考える時、SDGsという世界的な共通目標があると、これから世界が進んで行く大きな方向性というか潮流が見えるので、かえってやりやすいと感じたのが第一印象です。
SDGsに関しては、田舎の中小企業にしては早めに取り組むことができたので、内閣府からメールが届き、官民連携のプラットフォームへの参加を進めていただけました。(関連ブログ:内閣府からのメール>>)
今後ますます、インターネットを通じて、次々と価値観や情報が共有され、潮流が生まれ、大企業も中小零細企業も個人も世界規模で連携するような時代になります。
またグローバル化が進むことにより、私たちの生活や仕事は、どこかの国の戦争や政策の影響を更に受けやすくなります。
取り残されない為には情報感度を高めることが大切です。
まずは日経新聞を読むことからスタートしてみてください。40代の皆さんの、どのタイミングで家を買おうかな?それとも買わない方がいいのかな?住宅ローン金利は上がるかな?今後どんなスキルを身につけようかな?インフレはどうなるかな?今後の景気は?など身近なことを考える時の助けにもなるでしょう。
■大きな目標を達成する手段はコレ
40代の皆さんの大きな目標は何でしょうか?たとえば出世したい。大きな買い物をしたい。子供を大学にいかせたい。お金持ちになりたいとか独立したいとか?
私の40代の頃の目標は「会社をもっと成長させたい」でした。でも何をしたら良いのか分かりません。ですからさまざまな商品を次々に開発し、全く売れずに終わったことも数え切れません。今思えば、社会が求めているものではなく自己満足の商品を作っていたのです。
また自分自身の持っている知識の延長線上で商品開発をすれば良いのに、突飛な商品を開発したりしました。もちろん売れません。
また「手段」と「目的」が逆になってしまい、「会社の成長」ではなく「ヒット商品の開発」が目標になってしまった時期もありました。(余談ですが、手段と目的が逆になってしまう現象は、非常に多く発生します。これは最悪なので、定期的に目的を振り返ってみてください。関連ブログ:手段を目的と勘違いしてはいけない>>)
近年になって、ようやく分かったことがあります。
大きな目標を達成するためには、一足飛びを求めず、目の前のできることからコツコツ真面目にやっていくことが一番の近道なのです。目の前の課題を、毎日少しずつでも良いからアップデートし続ける。このアップデートを諦めず気が遠くなるまで繰り返すことです。
ちなみに「諦めず気が遠くなるまで繰り返す」は私の座右の銘です。そして13年前にこのブログを開始した一番初めに、このことについて書きました。(関連ブログ:諦めず気が遠くなるまで繰り返す>>)。それぐらい重要だということです。
もう一度書きます。
大きな目標を達成する手段は、
「目の前の課題を、毎日少しずつでも良いからアップデートし続ける」×「それを諦めず気が遠くなるまで繰り返す」
受注でいえば、若い頃の私は、大口の仕事のためには東奔西走しましたが、小口の仕事は、手間が多くあまり儲けも出ないので気が進まないなと思っていた時期もありました。
それよりも一足飛びにヒット商品を生み出したいと考えていました。
小口の仕事も大きな意味を持っていることに気付いていなかったのです。
小口の仕事が積み重なることで、信頼を築き、将来的に大きなビジネスチャンスにつながること、そして一方で、小口の仕事を軽視してしまうと、お客様との関係が損なわれるリスクがあることに当時は気付いていませんでした。
このような失敗から、目の前のできることからコツコツ真面目に取り組んでいくことが最善の方法であるということを学びました。
まだもう少し書きたいことがありますが、長くなってしまったので今回はこの辺りで終わりにしましょう。
2025年
2月
27日
木
カオス的変化の中で生きる現代人の生存戦略

【1か月で激変する価値観】
これまで価値観の変化は長い時間をかけて、ゆっくりゆっくりと浸透し変化していくものでした。
しかし、トランプがアメリカ大統領に就任してから、まだ僅か1か月と少しだというのに、さまざまな分野で変化が起きています。
各国や各企業が目標に掲げていたSDGsについても、逆回転する大手企業が見られるようになりました。たとえばトランプ政権がパリ協定からの再離脱を表明すると、ゴールドマン・サックスなどの大手金融機関は、脱炭素を目指す国際的銀行連合から脱退し、石油産業などへの投融資を強化しています。また、アメリカ国内の企業も、化石燃料の生産を拡大しています。
たった1年半ほど前に、気候変動会議(COP28)で、日本は未だに化石燃料に大きく依存しているとバカにする意味で「化石賞」が贈られ、日本の政治家が「恥ずかしい」と述べていた記憶がありますが、その恥ずかしい方向へ、アメリカは動き始めました。
またSDGsの目標である「多様性」についても、トランプ政権は連邦政府のDEI(多様性、公正性、包括性)プログラムを終了する大統領令に署名しました。
これにFacebookのメタやAmazon、マクドナルドなどの大企業が追随して、多様性を推進する施策の中止を次々に発表しています。
ウクライナとロシアの戦争についても、この3年間、日本を含む西側諸国はウクライナの支援を行ってきましたが、トランプはウクライナのゼレンスキー大統領を「選挙なき独裁者」と重ねて呼んで強く批判し、ロシア寄りの発言を続けています。
またトランプは国連やNATOに対して懐疑的な姿勢を示しています。余談ですがトランプはWHOからの脱退も表明しています。
僅かな期間で、これまでの価値観を否定し、社会の方向性を変えようとしています。
このカオス的変化の社会に、多くの人が戸惑いを感じているかと思います。私もその一人です。
【変化の時代には、選択肢を複数持っている者が強い】
私の肌感覚では、つい1,2年ほど前までだと思いますが、「トヨタはいつまでもハイブリッド車に拘ったり、水素自動車に手を出してみたりして、肝心の電気自動車(EV)へのシフトが遅れている」として、多くの批判を受けていた記憶があります。
それが近年、EV車にさまざまな問題が浮上し、EV市場の成長が急激に鈍化し、最近はまたハイブリッド車の需要が高まっているそうです。
日産が窮地に陥っている要因の1つが、「ハイブリッドを一切無視し、完全にEV車へ移行を加速させたこと」と昨年末に批判されているのを見て、こんなに不確実性の高い社会で一点張りすることのリスクを感じずにはいられませんでした。
隣人が、マスコミが、皆が、社会が「こっちに進むぞー!!」と走っていても、数カ月でコロッと変わってしまう社会なのです。現代は。
また、トランプが自動車関税を現在の10倍の25%にするとの見通しを示していますが、アメリカ国内に完成品の工場を持っている自動車メーカーは、影響は少なくてすみます。
トヨタは世界中に工場があり、もちろんアメリカにも沢山の工場を持っているので、関税の問題や地政学的な問題が起きても、軸足を移せば対応することが可能です。
「トヨタが一人勝ち」と言われる成功の一因は、さまざまな面で幅広い選択肢を持っていることにあると感じます。
【企業も個人も選択肢を複数持とう】
トランプ政権になってから、「未来を予測することなんて無理だな」という思いが益々強まりました。そして一点張りすることのリスクを益々感じます。
選択肢を複数持って、時代の変化に合わせて軸足を変えながら、柔軟に迅速に変化し続けるしかないなと感じます。
個人の生き方に関してもそうです。
一旦話が逸れますが、私が人から言われて、がっかりする言葉の一つがコレです。
「やったことないので出来ません」
この言葉を発した瞬間、自分の可能性を自分で潰しています。
「今の小学生たちの65%は、大学卒業時に今は存在していない職業に就くだろう」という予測があるそうです。
今自分がやっている仕事は、5年後10年後には、もう世の中には無いかもしれません。これほど変化が激しい社会を、「経験がある仕事」という手持ちの札だけで生きて行こうとすれば、みるみるうちに選択肢は減る一方です。
やったことが無い業務にも、どんどん挑戦すれば、手持ちの札は増えます。
転職する時にも「こんな経験もある。こんな業務も、あんな業務もやった。こんな役職にも就いていた」と自分を売込むことも出来ます。経験は自信にもつながります。
近年、リスキリング(新しいスキルや知識を学び直すこと)の必要性が叫ばれおり、政府も支援金を出すなどしていますが、実際のところ、何を学んだら良いのか分からない、学びたいものも無い・・・と思う人も少なくないはずです。
そんな場合は、まずは今の会社で求められているスキルを学めば良いのではないでしょうか?そうすればお給料も上がるかもしれません。そのスキルを持って転職することも可能でしょう。
カオス的変化の中で生きる現代人の生存戦略は「選択肢を増やすこと」だと私は思います。選択肢を増やすために、失敗を恐れず、どんどんやったことがない事や仕事や業務や役職にも挑戦していってほしいと思います。そうして自分の手持ちの札を増やせば、社会が変化しても生きていけます。
「やったことないので出来ません」は自分の可能性を自分で潰す言葉です。
誰でも最初は「やったことが無い」のです。たくさん失敗したり、赤っ恥をかいたり、周りに迷惑をかけたりしながら、「最初から何でも出来たベテランです」みたいな顔をしているわけです。
私だって、テキスタイル事業も、クリーニング事業も、繊維再生事業も、シニア事業も、社長業も、全部やったことはなかったです。笑
2025年
1月
22日
水
人口減少社会で生き残るには「戦略的縮小」

【2030年】
先日、電動歯ブラシを買いました。5年保証でしたので保証期間が2030年の1月なのです。
それまで2030年と聞くと、「まだ先の未来」という印象でしたが、保証書を見た瞬間「すぐそこの将来」なんだと一気に現実感を持ちました。
その2030年には日本の人口の約3分の1が65歳以上の高齢者になると推定されています。現在でも人手不足が叫ばれていますが、2030年には少子高齢化による人口減少や労働人口の減少が更に深刻なものになると予想されています。購買力のある消費者層が縮小するため、需要の低下から国内市場規模の縮小も予想されています。
【50年後・100年後】
厚生労働省の推計によると、日本の総人口は50年後に約8,700万人、100年後には中位推計で4,900万人になるとされています。
しかしこの数字は年金など社会保障の観点から計算されているため政治も絡み、かなり現実離れしている甘い仮定に基づいて出されている数値だそうです。
人口問題の第一人者である「人口減少対策総合研究所」理事長 河合雅司氏によると、直近5年間の出生数は毎年4.54%ずつ減少。このペースで減り続ければ、日本人人口は50年でなんと半減、100年後に1500万人という衝撃的な数字を出されています。
外国人の活用の是非が問われていますが、そんな対策では全く追いつかないほど日本人は激減して行く予測です。
インバウンド向けや輸出事業を行っている企業以外は、これからどんどん消費者が減って行きます。もちろん働き手も減ります。
そこで提唱されているのが「縮んで勝つ」「戦略的縮小」なのです。
【戦略的縮小】
このキーワードを目にした時、私は気分が高揚し、そして満足感を覚えました。というのも昨年一年間をかけて取り組んでいたこと、そしてこれから先、私が行っていこうとしている事に名前が与えられたような思いがしたからです。
昨年のブログにも書いたように、事業部の統廃合、不採算製品の製造中止、製品ラインナップの整理、利益率の高い商品の強化、そして新たに導入した機械設備と従来の設備を組み合すことによる新製品の開発・効率化など予定していたものは昨年中に全てやり終えました。
これから行っていく事は、従業員一人あたりの利益の拡大です。つまり生産性の向上。
これまで私も含め経営者は、売上やシェアを伸ばすことを意識していたと思います。しかしこれは、人口が拡大していく社会での考え方。
消費者も働き手も減っていく社会では、従業員一人あたりの利益を拡大していくことが重要。
現在、大手企業、しかも黒字企業の構造改革による大量リストラがニュースでも毎日のように取り上げられていますが、その一方、人手不足倒産は調査を開始した2013年以降の過去最多を、2年連続で大幅に更新したそうです。
少ない人数でも生産力を維持できる企業になるため、繊維事業部については設備投資を行い、生産効率が大幅に向上しました。(詳しくはこちら>>)
そして今取り組んでいるのが本社の経理業務のDX化です。
すでにDX化を進めていたつもりでいたのですが、「丸竹さんのソフトは平成の最新鋭で、令和から見たらもう古い」というようなご指摘を受けたため、それならばと、どこの会社のものを導入するか現在見積もりを取って検討している最中です。
シニア事業についてはDX化は難しい業界だと言われています。確かに介護ロボットのようなものはまだ現実的ではないですが、事務作業をDX化し効率化することで、それ以外のことに時間を使えるようになります。シニア事業部については現在最新のソフトを導入していますが、何年か先にはもっと良いソフトが出てくるでしょう。その投資はしていこうと考えています。
DX化と聞くと中小企業の身の丈には合っていないような感覚を持つかたも少なくないかもしれませんが、人手を集めるのが難しい中小企業こそDX化を進めなければと思います。
5月のブログでは経費削減の取組みについて書きました。(詳しくはこちら>>)
トヨタの「改善後は、改善前」という言葉のように、経費削減の改善後も無駄が発生していないか永続的に改善を続けていくつもりです。
そして労働人口減少社会に向けて、これから進めていこうとしているのが「業務のスリム化」です。
DX化で効率を上げるのはもちろんのこと、慣例的に行っているだけの書類作成や会議や仕事を削減して行こうと思います。その業務は本当に必要なのか?もっと効率良くする方法はないのか?その回数必要なのか?等を見直していきます。
先般の衆議院選挙の折に公約の中で、最低賃金を2020年代に時給@1,500―/hにするとありました。
中小企業への最新のアンケートでは最多は、「不可能」の48.4%で、約5割の企業が最低賃金1,500円への対応が困難と回答したそうです。しかし私は「戦略的縮小」で、合理化を進め、経費の無駄の削減、業務のスリム化、利益率の高い商品の強化などによって、最低賃金1,500円への対応を可能にしたいと考えています。
また社内の評価制度や勤務体制の見直しを図り、公正で「損している気分にさせない」透明性のある評価制度を導入し、社員の努力や成果を評価し、給料に反映していきたいと考えています。
会社が成り立つのは、働いてくれる社員のおかげです。ですから、頑張ってくれる社員一人一人を大切にしたいと考えています。そして会社が成り立つ為には、商品やサービスを購入してくださるお客様の満足があってこそですので、社員と共に精一杯力を尽くしてまいります。
本年も皆様方のご指導・ご厚情を賜りますようどうぞよろしくお願い申し上げます。皆様方のご多幸とご健康を心よりお祈り申し上げる次第であります。