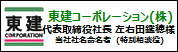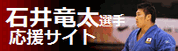当社が製造事業部門で、障害者の雇用を始めるようになって数年経った頃、たしか平成7年頃の話である。
大阪府立砂川厚生福祉センターの先生の紹介で、大阪府立佐野養護学校(当時)から、I君という20歳の男子卒業生を真空パック工場で雇って欲しいとのご依頼があった。
I君は身体的には何の障害も無いのだが極度の自閉症であり、お母さんとは何らかのコミュニケーションが有るらしいが、母親以外の人とは一言も話さないし、担任の先生とも入学以来、言葉はおろか目も合わせたことが無いという事であった。
その後、I君は担任の先生に付き添われて面接のために来社してきた訳だが、事前に聞いていた通り一言も話さないばかりか、確かに目も合わさない青年であった。
自閉症の方の雇用は初めてだったので不安はあったが、ハンディキャップがある人に対しても雇用の機会を創出していく事が、経営者の「義」であり社会的責任と考えていたので、その場で採用を決めた。
当時の真空パック工場の責任者であったM工場長と対応を協議した結果、「最初は特別なことはせず、すべてに渡りごく普通に接しよう」「その後、状況を見ながら判断して行こう」という事で意見が一致して、いよいよ出勤初日を迎えたのであった。
桜の季節、I君はお母さんと共に出社してきた。
「息子が慣れるまで暫くの期間、私も8時間、工場に居ても良いでしょうか?」という事前の申し出があった為、他の社員達にも事情を話し、皆が快諾していた。
椅子を勧めてもお母さんはI君のすぐ傍に立ち、息子の作業に間違いがないか、終業までの8時間、見守り続けた。
このような事は初めてだったので私は少し困惑した。
翌日も、その翌日も、お母さんは椅子を断り、I君の作業を傍で見守った。
途中から気づいたのだが、トイレもI君の休憩時間に合わせて行くほどであった。それほど片時も息子から目を離さなかった。
お母さんのやり方が正しいのか間違っているのか、そんなことは私には分からない。
しかし、悲壮なまでの責任感と全身全霊をかけた愛情を、私は見たおもいだった。
お母さんは5月になっても毎日工場に来てI君を見守り続けた。
この頃には、工場の隅の椅子から彼を見守っていた。
日によっては午前中に家事や用事を済ませてから来る日もあったが、毎日朝から夕方まで工場で過ごすのは大変なご苦労だったと思う。
I君のコミュニケーション能力については1か月経っても何ら代わり映えしなかったが、業務内容については単純作業という事もあり何の問題も無く、他の社員と変わりなく働いた。
お母さんは6月になっても毎日工場に来ては片隅に座っていた。
ある日、私はお母さんに「もう見守る必要がないのでは?」と言うと、
「すみません。家に居ても心配で心配で何も手につかないんです。ここで息子を見守ってる方が、気持ちが楽なんです。」と返ってきた。
梅雨が終わって、夏が本格的に始まっても、お母さんは毎日工場に来た。片隅の椅子に座って本を読んだりしながら、合間合間に顔を上げて、I君を見守っていた。
私はその姿を見る度に、母の子に対する慈愛の深さに驚くと同時に、亡き母を思い出して郷愁を覚えた。
その年の秋になって繁忙期に差し掛かると、真空パック工場は猫の手も借りたいほど忙しくなった。I君のお母さんは相変わらず工場に通って来ていた。
そこで私は「人出が足りなくて困っています。お母さん、出来れば当社で短期アルバイトとして働いてもらえませんか?」と声を掛けさせてもらった。
人手に困って出た言葉であったが、お母さんは「ほんとにいいんですか!?」と快諾してくれ、その日から一緒に働いてくれた。
この後、数日してI君にある変化が訪れた。
それまでは一日中、たとえお母さんとでも、社内ではほとんど無いに等しかったコミュニケーションが、仕事中にお母さんとは何らかのコミュニケーションを若干しているのである。
私にはそれがI君の小さな進歩に思えた。
秋も終わり、冬が始まり、正月も過ぎ、春の気配を感じる頃、I君はまた少し変わった。
「おはよう」と声を掛けると、今まで完全に固まっていたI君であったが、目は合わせないが小さく頷くようになったのである。
春になり真空パック工場の繁忙期は終わったが、もうそのままお母さんはパートとしてI君と一緒に働いてもらうことにした。
I君は、畳の目を数えるような変化ではあったが、少しずつ少しずつ変わって行った。
それまでずっと無表情だったのが、声をかけると口角を少し上げるようになった。また一瞬ながらも、こちらの顔を見ながら頷くようになった。
2年半が経つ頃には、毎朝「おはよう」と声を掛けると、何らかの唇の動きを見せて、一瞬こちらに視線を向けて若干の笑顔を見せてくれるようになった。
3年が過ぎた頃、I君のお父さんが転勤することになり、I君もお母さんも退職することとなった。
退職する最後の日に、私が一か八か握手を求めると、I君は手を差し出してきた。
たかが握手かもしれないが、最初の頃のコミュニケーションを思えば考えられないことであった。
私が手を握ると、I君はまたうつむいてしまったが、間違いなく握り返してきた。
そのI君の姿を見てお母さんは泣いていた。私も感動して涙が出た。
I君の成長が嬉しかった。最初の頃、きっと不安な気持ちで工場の片隅の椅子に座り続けたお母さんが今喜んでいる姿が嬉しかった。
この時の経験が、今も継続して障害者雇用に積極的に取り組んでいることに繋がっている。
当時、「障害者本人の個性に、周りが寄り添う気持ちさえあれば、その個性は良い方に変化して行く」という事に確信を持つに至った次第である。
●第3回フラワーホームカップを開催いたしました。